問 題
我が国における耕地の利用と栽培管理、収穫に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1.水田は畑に比べて連作障害が発生しやすいため、水田を畑として利用する田畑輪換栽培が行われている。圃場を幾つかのブロックに区分けし、一つのブロックで 2 種類の作物を時期をずらして栽培するブロック・ローテーションの仕組みが導入されている。
2.イネの移植から収穫までに必要となる水量全体を用水量という。用水量は、イネの体内水量、葉からの蒸散量、田面蒸発量、地下浸透水量、漏水量、降水量の合計で表される。灌漑水を最も多く必要とする時期は有効分げつ期である。
3.ダイズの栽培では、一般に、除草や倒伏防止、排水の促進を目的として、開花期までに中耕・培土が行われる。大規模な経営では、ダイズの収穫にコンバインを用いる場合が多い。
4.コムギの発芽に必要な低温要求度を秋まき性程度という。越冬前の生育量確保のため寒冷地では秋まき性程度の低い品種が栽培されている。北海道の寒さの厳しい一部地域では、秋まき性程度の低い品種を用いた春まき栽培が行われる。
5.イネを自脱コンバインで収穫する場合には、刈取り後、動力脱穀機での脱穀を行う。脱穀後は籾すり作業を行い、その後、乾燥作業、くず米の選別作業を行う。
解 説
選択肢 1 ですが
イネの水田作 (湛水栽培) には、リン酸の無効化が少ない、連作障害が起きにくい、土壌の塩類集積や侵食がほとんどないなどの利点があります。(参考 H27 no10 選択肢 3 https://yaku-tik.com/koumuin/h27-nougaku-10/ )「水田は畑に比べて連作障害が発生しやすい」という記述は不適切です。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 ですが
第 1 文は妥当と考えられます。田植えから収穫までに必要な水量が用水量です。「用水量 = 葉面蒸散量+田面蒸発量+地下浸透・漏水量ー有効降水量」と表されます。「降水量を合計、つまり足し合わせて表す」わけではありません。
また、灌漑水を最も多く必要とするのは「穂ばらみ期」です。分げつ期には中干しや、かんがいと落水を繰り返す間断かんがいをおこなうことからも、水をそれほど必要としない時期と判断できるのではないでしょうか。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 は妥当です。
ダイズの栽培についての記述です。
選択肢 4 ですが
第 1 文に関して、秋まき性程度は 花芽 (穂) の分化に必要な低温の程度です。発芽は「種子から芽が出てくること」です。第 1 文は不適切です。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 ですが
自脱型コンバインは、稲や麦を刈り取りながら脱穀する機能を備えた農業機械です。刈取りとほぼ同時に脱穀が行われます。「刈取り後、動力脱穀機での脱穀を行う」わけではありません。また、脱穀 → 乾燥 → 籾すり という流れです。籾すりは、籾から籾殻 (もみがら) を取り除き 玄米にする作業です。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 3 です。
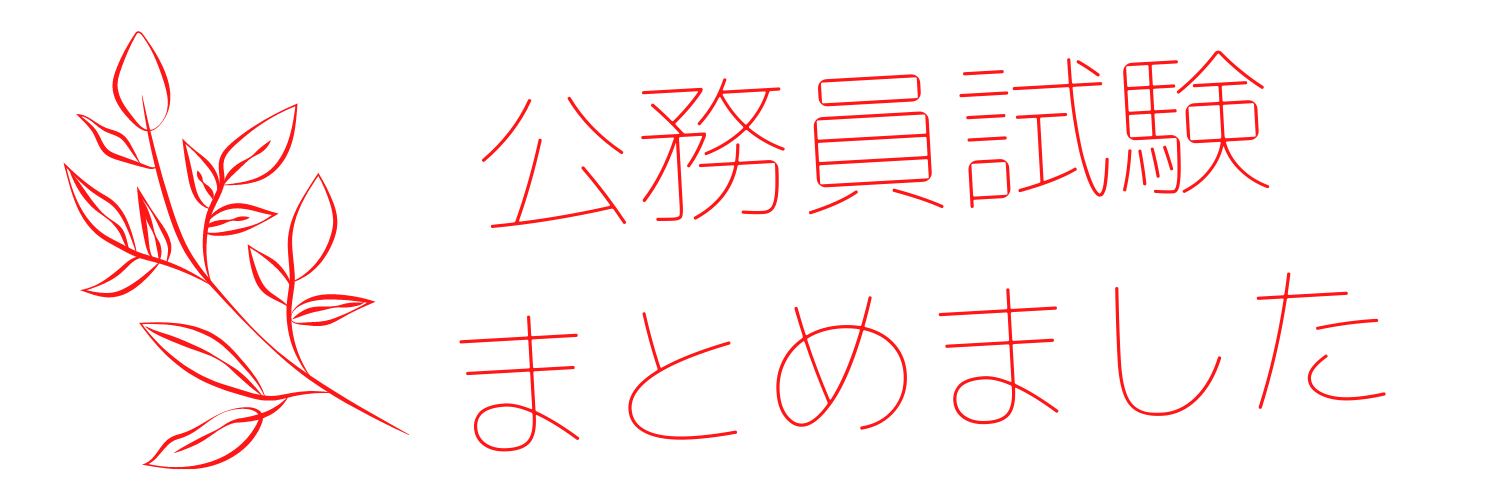
コメント