問 題
作物の成長解析と収量形成に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1.吸光係数とは、個体群内の光環境を数値として評価する指標であり、この値が小さいほど光が個体群内に良く到達することを示す。吸光係数は、一般に、マメ科作物のような水平に広がる葉が多い個体群よりもイネ科作物のような直立葉が多い個体群で値が小さい。
2.葉面積指数とは、個体群の総葉面積に対する総乾物重の比であり、個体群光合成速度を支配する要因の一つである。個体群光合成速度は、栽培期間を通じて葉面積指数の増加に伴って常に増加する。
3.相対成長速度は、一定期間内の単位乾物重当たりの乾物生産量で、単位葉面積当たりの乾物増加速度と個体群の全葉面積の積で表される。相対成長速度は、乾物重が異なる群落間の比較が難しく、これを補う指標として、単位土地面積当たりの乾物生産速度である個体群成長速度がある。
4.イネの収量構成要素は、単位土地面積当たりの穂数、登熟歩合、 1 穂籾数、千粒重であり、穂数と登熟歩合は栄養成長期に、 1 穂籾数と千粒重は出穂期の終わりから登熟期にそれぞれ決定される。
5.多収を目的として育成されたイネ品種の収量向上は、作物体の総乾物生産量の増大よりも乾物の穂への分配割合の増加によるところが大きく、収穫指数は必ずしも高くはない。ソースサイズの拡大が収量向上の大きな要因となっている。
解 説
選択肢 1 は妥当です。
農学における吸光係数についての記述です。「値が小さいほど光が個体群内に良く到達することを示す」という点をおさえておきましょう!
選択肢 2 ですが
葉面積指数 (ようめんせきしすう) は「葉の総面積 ÷ 土地面積」です。「個体群の総葉面積に対する総乾物重の比」ではありません。
また、葉面積指数がある程度増加すると、葉の重なりによって光合成速度は頭打ちになったり、減少したりすると考えられます。「常に増加する」わけではありません。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
相対成長速度が「一定期間内の単位乾物重当たりの乾物生産量」、個体群成長速度が「単位土地面積当たりの乾物生産量」という部分は妥当です。相対成長速度は、個体乾燥重量を wとすると、1/w・dw/dt です。「単位葉面積当たりの乾物増加速度 と 個体群の全葉面積の積」ではありません。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが
イネの収穫構成要素が「単位土地面積当たりの穂数、登熟歩合、 1 穂籾数、千粒重」というのは妥当です。
イネの生長は、栄養生長期、生殖生長期 および 登熟期 の 3 つに分けられます。登熟歩合が決まるのは登熟期だろうというのが判断しやすいと思われます。選択肢 4 は誤りです。
補足すると、穂数は栄養成長期間に、登熟歩合は出穂 ~ 登熟初期、籾数は 生殖成長期に決定されます。千粒重は品種ごとに比較的安定している要素です。ある程度は登熟期間の環境に左右される程度です。
選択肢 5 ですが
収穫指数 (収穫係数) とは、収穫部重を作物体全重で割った値です。イネ品種の収量向上は、多粒穂化によるシンクサイズの拡大に伴う収穫指数増加が貢献しています。また「ソースサイズの拡大が…大きな要因」とはいえず、選択肢 5 は誤りと考えられます。
以上より、正解は 1 です。
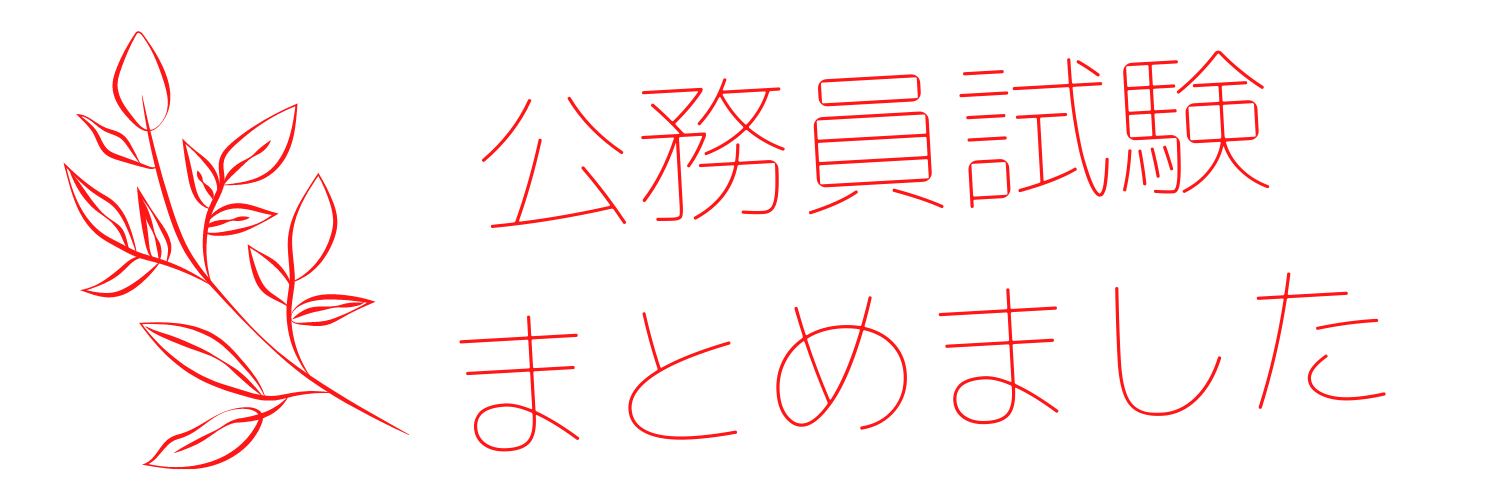
コメント