大気中の粒子状物質に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 大気中の粒子状物質は、降下ばいじんと浮遊粉じんに大別される。
- 工場、自動車などから排出される一次粒子と大気中で生成する二次粒子がある。
- 粒子径が10μm以下の粒子状物質を浮遊粒子状物質と呼ぶ。
- 粒子径が2.5μm以下の粒子状物質を微小粒子状物質と呼ぶ。
- 微小粒子状物質の主な成分は、物の粉砕で発生する粉じんである。
正解 (5)
解 説
微小粒子状物質とはPM2.5のことです。物の粉砕で発生する粉じんでも、粒子径が2.5μm以下であれば微小粒子状物質に該当しますが、主たる原因は別にあります。
微小粒子状物質の主な発生源は工場などの煙突から出る排ガスで、成分としてはSOx、NOx、揮発性有機化合物(VOC)などに由来する粒子が挙げられます。
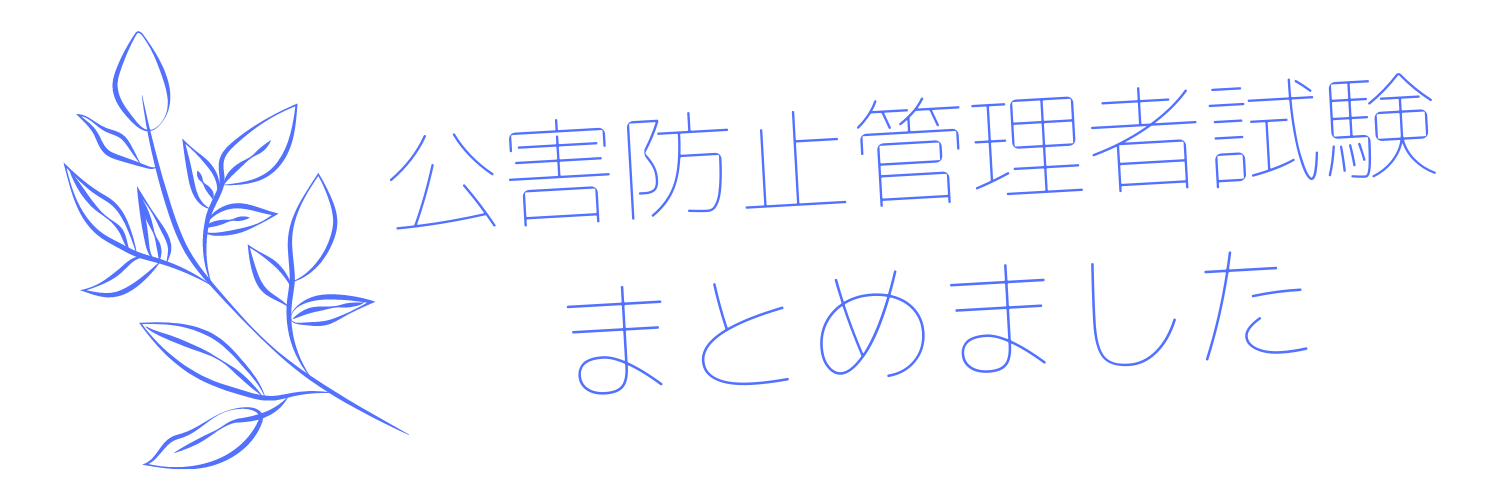
コメント