問 題
電力系統に現れる過電圧(異常電圧)はその発生原因により、外部過電圧と内部過電圧とに分類される。
前者は、雷放電現象に起因するもので雷サージ電圧ともいわれる。後者は、電線路の開閉操作等に伴う開閉サージ電圧と地絡事故時等に発生する短時間交流過電圧とがある。
各種過電圧に対する電力系統の絶縁設計の考え方に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 絶縁協調とは、送電線路や発変電所に設置される電力設備等の絶縁について、安全性と経済性のとれた絶縁設計を行うために、外部過電圧そのものの大きさを低減することである。
- 避雷器は、過電圧の波高値がある値を超えた場合、特性要素に電流が流れることにより過電圧値を制限して電力設備の絶縁を保護し、かつ、続流を短時間のうちに遮断して原状に自復する機能を持った装置である。
- 架空送電線路の絶縁は、外部過電圧に対しては、必ずしも十分に耐えるように設計されるとは限らない。
- 送電線路の絶縁及び発変電所に設置される電力設備等の絶縁は、いずれも原則として、内部過電圧に対しては十分に耐えるように設計される。
- 発変電所に設置される電力設備等の絶縁は、外部過電圧に対しては、避雷器によって保護されることを前提に設計される。その保護レベルは、避雷器の制限電圧に基づいて決まる。
解 説
(1)が誤りです。電力系統の絶縁設計における「絶縁協調」とは、送電線路や発変電所に設置される各種電力設備の絶縁耐力と、現れる過電圧(外部過電圧や内部過電圧)の特性に基づき、適切な耐電圧レベルを決定するための設計手法です。
つまり、各機器の絶縁レベルが、現実に発生しうる過電圧に対して十分な余裕を持ちつつも、過剰な設計にならないよう安全性と経済性を両立させるものです。
ここで、(1)では「外部過電圧そのものの大きさを低減することである」とありますが、絶縁協調は外部過電圧の大きさを直接低減するのではなく、例えば避雷器などを用いて過電圧を一定値以下に抑制することで機器の保護を行っています。
(2)は正しいです。避雷器は、過電圧が特定の波高値を超えた際に、内部の特性要素により電流が流れて過電圧を制限し、その後すぐに原状に復帰する機能を持つ装置です。
(3)も正しいです。架空送電線路の絶縁は、外部過電圧に対して必ずしも十分に耐えるよう設計されているとは限らず、実際は避雷器などの保護対策に依存している面があります。
(4)も正しいです。送電線路や発変電所の設備は、内部過電圧(開閉サージなど)に対しては原則として十分に耐えられるように設計されています。
(5)も正しいです。発変電所の設備は、外部過電圧に関しては避雷器による保護が前提とされ、その保護レベルは避雷器の制限電圧に基づいて決定されます。
以上から、正解は(1)です。
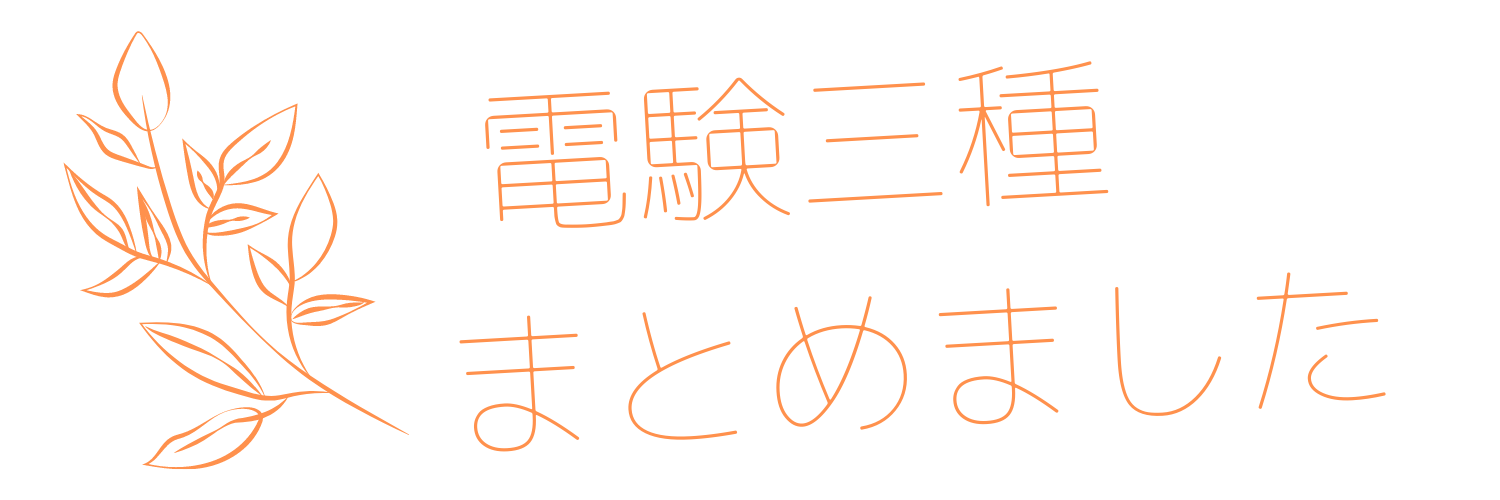
コメント