問 題
架空送電線の振動の特徴と対策に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 送電線の上下配列にオフセットを設けて、電線どうしが接触しないようにする方法がある。
- 電線に当たる一様な微風により、電線の背後に空気の渦が生じ、電線が上下に振動する現象を微風振動といい、これを抑制する方法としてダンパの取付けがある。
- 電線に付着した氷雪の断面が非対称になり、これに風が当たることで発生する揚力の影響で、電線が振動する現象をギャロッピングといい、多導体では発生しにくい。
- 多導体の送電線に風速10m/sを超える風が当たることで、多導体の素導体が不安定になり電線が振動する現象をサブスパン振動という。
- 電線に付着した氷雪が脱落し、その反動で電線がはね上がる現象をスリートジャンプという。
解 説
(1)は正しいです。送電線の上下配列にオフセットを設ける方法は、電線が大きく振動したときに互いに接触するのを回避するための基本的な対策といえます。
(2)も正しいです。比較的ゆるやかな風が電線に対して直角の方向に吹くと、その電線の風下側にカルマン渦という気流が生じ、これによって電線が上下に定常的に振動します。これが微風振動と呼ばれる現象です。
微風振動の対策としては、ダンパやアーマロッドなどの防振装置をつけることが効果的です。ダンパは振動の吸収材となり、アーマロッドは電線の補強の役割を果たします。
(3)が誤りです。
ギャロッピングは、電線に雪や氷がくっついたところに風が吹いてきた際に起きる現象です。雪などによって電線が重くなっていることに加え風を受ける面積が大きくなっているため、その振動も大きくなります。電線の振動幅が大きいと、悪いときには電線同士が接触してショートすることもあります。
ここで、単導体と多導体を比べると、単導体はそれ自体が回転できるので雪や氷が付きにくい(落ちやすい)ですが、多導体の場合はスペーサがあって回転できないので氷雪が付きやすいといえます。
そのため、多導体のほうがギャロッピングを起こすリスクが高いため、(3)の最後に書かれている「多導体では発生しにくい」という部分が誤りです。
(4)は正しいです。サブスパンとは、スペーサとスペーサで区切られた区間のことです。多導体の架空送電線において、風速が数~20m/sでサブスパンの電線が振動し始め、特に10m/sを超えると激しく振動することがあります。この現象をサブスパン振動といいます。
(5)も正しいです。スリートジャンプは、電線の上に積もった雪が落下する際、その反動で電線が跳ね上がる現象を指す言葉になります。ギャロッピング同様に電線が大きく揺れるので、電線同士が接触してショートをするなどの危険があります。
以上から、正解は(3)となります。
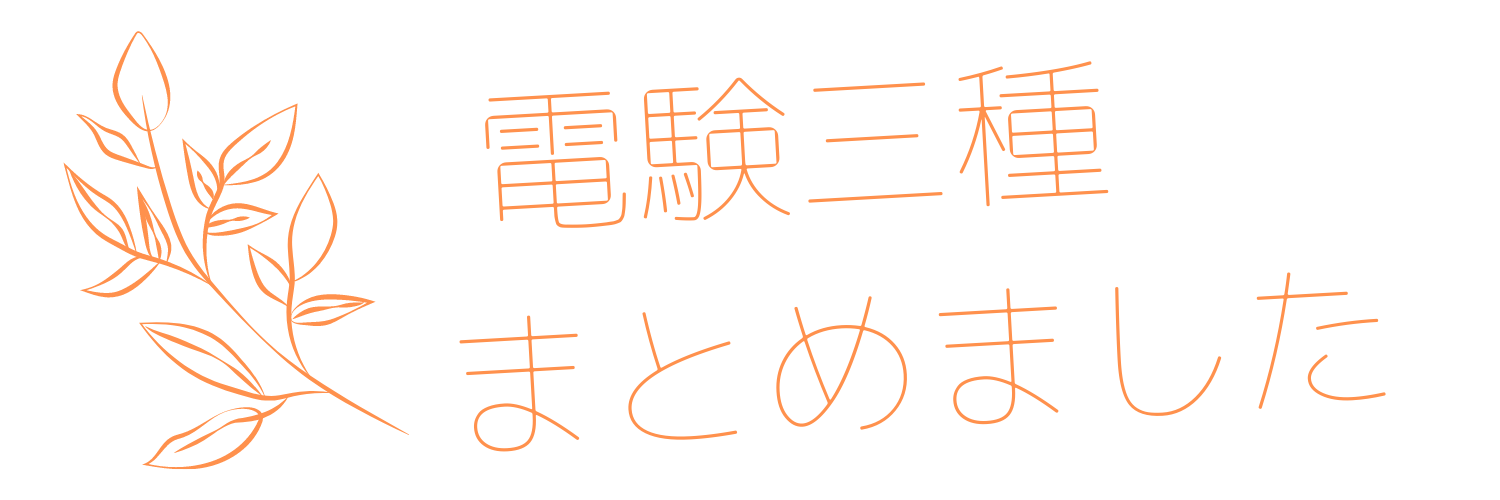
コメント