問 題
燃料電池の原理と特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 燃料は外部から供給され、直接、交流電力を発生する。
- 電解質により、りん酸形、溶融炭酸塩形、固体高分子形などに分類される。
- 水の電気分解と逆の化学反応を利用した発電方式である。
- 発電時の排熱を空調や給湯に活用できる。
- 天然ガスやメタノールを改質して発生させた水素を燃料として利用できる。
正解 (1)
解 説
(1)が誤りです。燃料電池は、外部から供給された燃料(主に水素)と空気中の酸素との化学反応により、電気エネルギーと熱エネルギーを発生させる装置です。
そのため、燃料が外部から供給される点は正しいですが、発生するのは直流電力(DC)です。これを交流電力(AC)にするには別途インバータなどを用いる必要があるため、(1)の「直接、交流電力を発生する」という記述は誤りです。
(2)は正しいです。燃料電池は電解質の種類によって分類され、代表的なものにりん酸形燃料電池、溶融炭酸塩燃料電池、固体高分子形燃料電池などがあります。
(3)も正しいです。燃料電池は、水の電気分解で分解される水素と酸素を再結合させる反応を利用して発電します。
水を電気分解するためには結構なエネルギーを外から加えなければいけませんが、裏を返せば、水素と酸素を反応させて水にすれば、結構なエネルギーが取り出せるということになります。
(4)も正しいです。燃料電池は比較的高い熱効率で電気とともに熱を発生するため、その排熱を有効利用し、コージェネレーション(熱電併給)に活用できます。
(5)も正しいです。記述の通り、実際に運用されている多くの燃料電池システムでは、天然ガスやメタノールの改質プロセスにより水素を得て、それを燃料として利用しています。
以上から、正解は(1)となります。
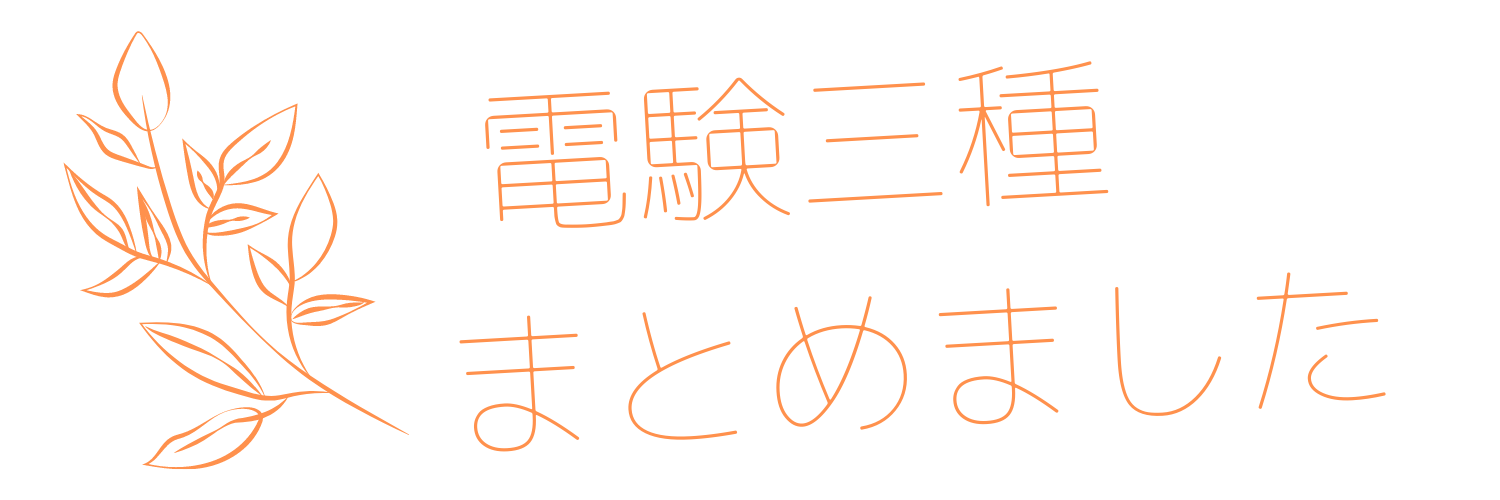
コメント