問 題
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- ダクトの支持点間の距離を2m以下で施設した。
- 造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
- ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクトの内部に塵埃(じんあい)が侵入し難いように施設した。
- 5mのダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。
- ダクトを固定せず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した附属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。
正解 (1)
解 説
本問は「電気設備技術基準の解釈」第165条(特殊な低圧屋内配線工事)3項からの出題です。出題頻度からみてもそこまで重要とはいえないテーマなので、ご自身の学習状況や理解度によっては後回しにしても構わないと思います。
(1)は正しいです。ライティングダクトは2m以内ごとにしっかりと支持を取ることが求められています。これは、ダクトを確実に支持し、垂れやねじれが生じないようにするためです。
(2)は誤りです。ここでは造営材を貫通する場合の諸々が書かれていますが、ライティングダクト工事による低圧屋内配線では、そもそもダクトが造営材を貫通することを認めていません。
そのため、この文章は一部が誤っているのではなく、「ダクトは、造営材を貫通しないこと」のように全面的に書き直さないと正しい文章となります。
(3)も誤りです。ダクトの開口部を上に向けると塵埃が入りやすくなり、これを阻止するのは困難です。そのため、ダクトの開口部は下に向けることが基本となります。条件次第では横向きにもできますが、上向きにはできません。
(4)も誤りです。わざとらしく「電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった」と書いているので判断しやすいと思いますが、実際には、このような装置を施設することが求められています。
(5)も誤りです。ダクトは造営材に堅ろうに取り付ける必要があり、記述のように固定せず使用することは認められていません。
以上から、正解は(1)となります。
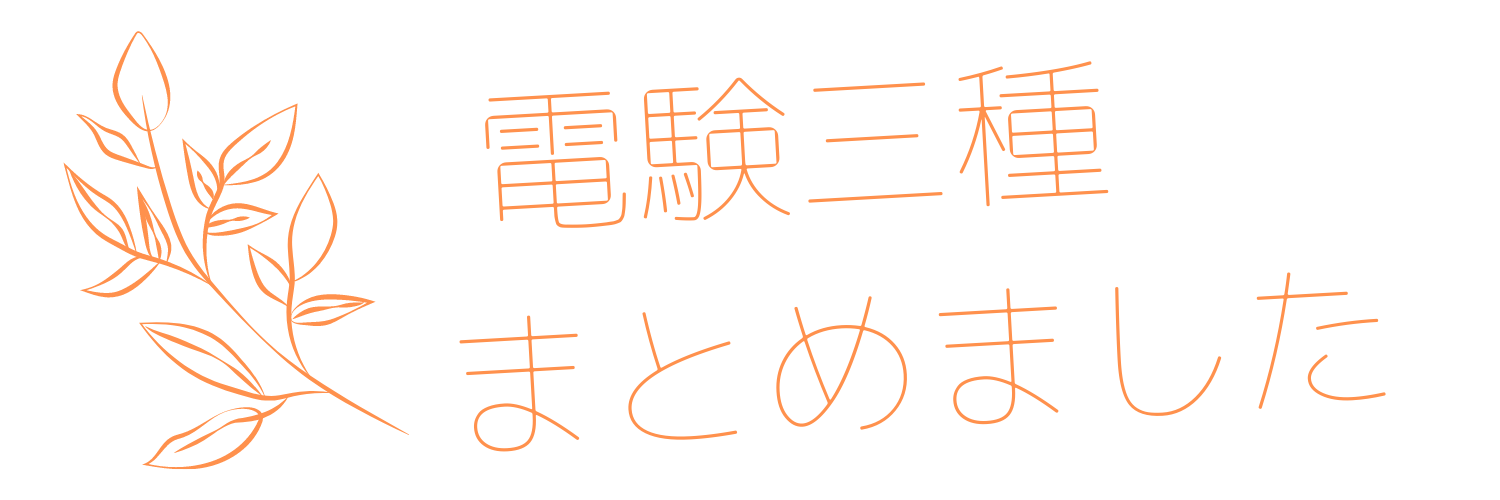
コメント