問 題
ねずみ・昆虫やその防除に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- ノミバエ類とショウジョウバエ類の発生源は同じである。
- 昆虫成長制御剤(IGR)による羽化阻害効力は、LC50の数値で評価される。
- ねずみと昆虫では、薬剤抵抗性の発達の原理が異なる。
- ヒアリ類は、要緊急対処特定外来生物に指定されている。
- 建築物環境衛生維持管理要領には、IPMの考え方に基づく動物種別の防除法や防除手順が具体的に示されている。
解 説
(1)は誤りです。ノミバエ類は腐敗した動物質が、ショウジョウバエ類は腐った果物や腐敗した植物などが発生源となります。ただし、ノミバエ類もショウジョウバエ類も出題頻度は低いので、この選択肢は気にしなくてもいいかもしれません。
(2)も誤りです。昆虫成長制御剤(IGR)による羽化阻害効力は、「LC50」ではなく「IC50」で評価されます。
KT50、IC50、LD50、LC50の用語の意味は以下の通りですが、これらの区別は重要なので、ぜひ優先的に押さえておきたい知識です。
KT50は「Knock-down Time, 50%」の略で、全体の50%がノックダウンする時間を示しています。これは、殺虫剤の速効性を示す数値となります。
IC50は「Inhibitory Concentration, 50%」の略で、50%阻害濃度と訳されます。50%の幼虫が成虫になるのを阻害され、成虫になれなくする濃度のことです。
LD50は「Lethal Dose, 50%」の略で、日本語にすると「半数致死量」のことです。その薬をある一定量投与したときに対象動物(虫)の半数が死んでしまう量を指すので、この半数致死量が少なければ、「少量の毒で死ぬ=強力な毒」ということになります。
LC50は「Lethal Concentration, 50%」の略で、日本語にすると「半数致死濃度」のことです。空間中や水中にある薬を撒いたり溶け込ませたりしたとき、対象動物(虫)の半数が死んでしまう濃度を指します。LD50は直接投与する量ですが、LC50では環境中の濃度であることがポイントです。
(3)も誤りです。ねずみや昆虫を含め、生物に薬剤を繰り返し使用すると、遺伝子突然変異などによって抵抗性を有する個体が増え、薬剤が効きにくくなる薬剤抵抗性の発達が起こります。
これは基本的に自然選択の原理であり、「遺伝的変異を持つ個体が生き残って繁殖する」という点で、抵抗性が発達する仕組みは全ての種で同じといえます。
(4)は正しいです。ヒアリ類は各地の港湾地区で発見されていて、皮膚炎の被害が懸念されています。そのため、要緊急対処特定外来生物に指定されています。
(5)は誤りです。建築物環境衛生維持管理要領に記載されているのは、概略的・総論的な説明が多いです。そのため、「動物種別の防除法や防除手順が具体的に示されている」わけではありません。
以上から、正解は(4)となります。
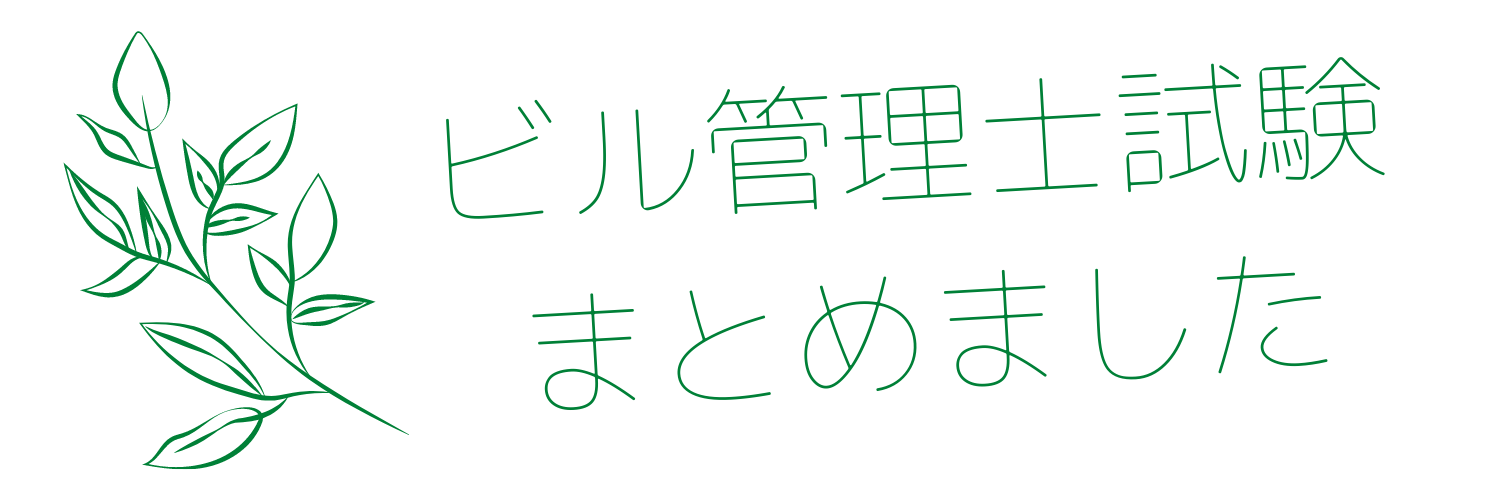
コメント
解説の最後の6行が消し忘れと思われます。
修正しました。ご指摘ありがとうございます!