問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物内のねずみ・昆虫等の防除に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- ニューサンスコントロールとは、感染症の媒介を断つための手段として行うねずみ等の防除である。
- IPMにおける「許容水準」とは、放置すると今後、問題になる可能性がある状況をいう。
- IPMに基づくねずみ等の防除では、定期的・統一的な薬剤処理を行う。
- 調査では、被害状況に関する聞き取り調査を重点的に行えばよい。
- ねずみ等に対する対策を行った場合、有害生物の密度調査などによって、その効果について客観性のある評価を行う。
正解 (5)
解 説
(1)は誤りです。これは「ニューサンスコントロール」ではなく「ベクターコントロール」の説明文になっています。
ペストコントロールには、ベクターコントロールとニューサンスコントロールの二つの側面があります。それぞれの用語の説明は次の通りです。これもたまに出題されるので、以下の3つを区別できるようにしておきたいところです。
- ペストコントロール:害虫対策として行う防除のこと。
ペスト(pest)とは、ネズミや害虫などの有害な生物を指します。 - ベクターコントロール:感染症を媒介する害虫対策として行う防除のこと。
ベクター(vector)には、「感染症を媒介する害虫」の意味があります。 - ニューサンスコントロール:不快感をもたらす害虫対策として行う防除のこと。
ニューサンス(nuisance)には、「生活妨害」といった意味合いがあります。
(2)も誤りです。これは「許容水準」ではなく「警戒水準」の説明文になっています。
生息調査の結果として判定される水準には、以下の3つがあります。重要事項として、ぜひ抑えておきたい知識です。
- 許容水準:良好な状態で、このまま維持したい
- 警戒水準:現状で大した問題はないが、放っておくと問題が生じるかもしれない
- 措置水準:状況は悪く、すぐに防除作業が必要
(3)も誤りです。この試験でたびたび使われる「ねずみ等」という言葉は、「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」のことです。つまり、ねずみ以外にゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニなども含みます。
このように対象が様々である上、その発生数や発生した部屋の状況などもそれぞれなので、定期的・統一的な薬剤処理というのはあまり価値がありません。薬剤を不必要に乱用することなく、そのときの状況に応じた適切な薬剤処理が求められます。
(4)も誤りです。発生状況や被害状況に関する聞き取り調査も重要ですが、ねずみやゴキブリなど夜行性のものも多く、これらだけではカバーしきれない部分もあるので、トラップ等による捕獲調査も必要です。
(5)は正しいです。(4)の解説の通り、調査や評価は客観的な手法によるものが望ましいです。
以上から、正解は(5)となります。
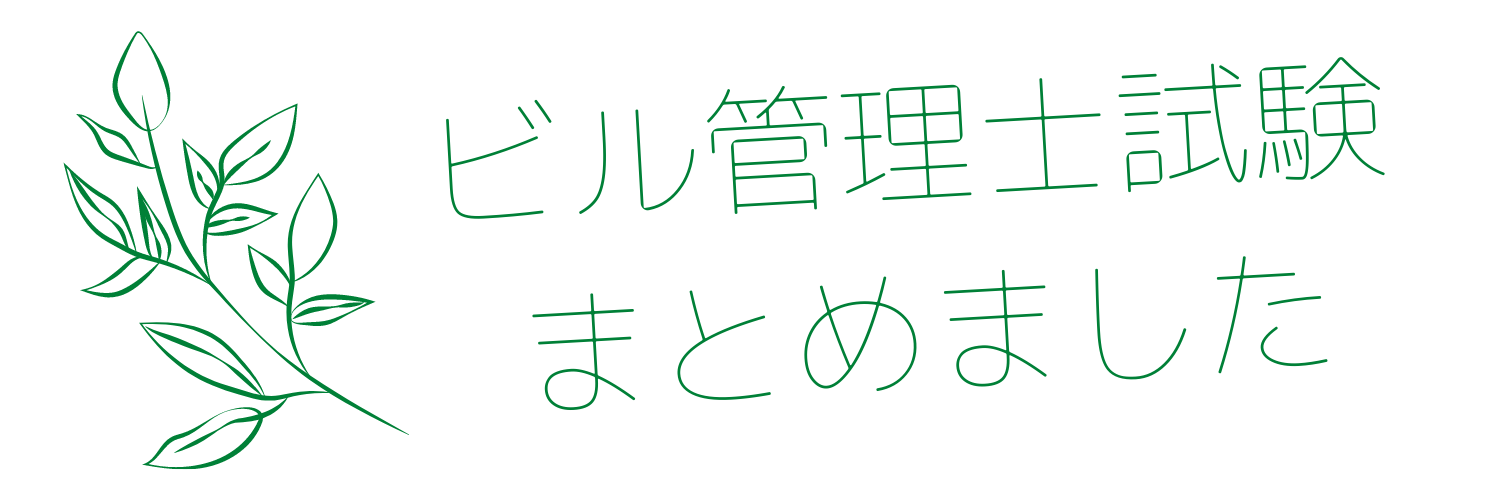
コメント